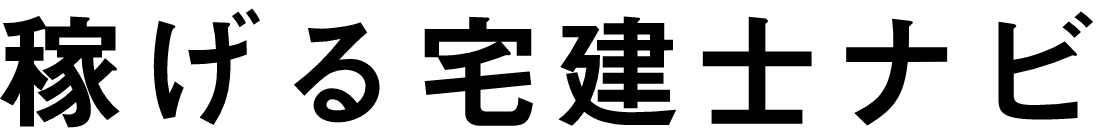今回の宅建士になるための過去問解説は、「業務上の規制」についてです。
前回の「報酬に関する規制」に引き続き、宅建業者の業務の規制になります。
宅建業者は、取引関係とのトラブル防止と保護のために、従業員に証明書を携帯させ、責任の所在を明確にしなければなりません。
また、事務所ごとに帳簿の備付け、及び取引のつど、帳簿に記載する義務があります。
ここで平成29年度の宅建士試験に出題された「業務上の規制」の問題を解いてみましょう。
問題35
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定よれば、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法49条に規定されている業者に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を帳簿に記載しなければならない。
(2)宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
(3)宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。
(4)宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業員名簿に記載しなければならない。
解答はこちらから「過去問の解答:業務上の規制」

Contents
宅建士の過去問解説【宅建業法】業務 ― 業務上の規制
業務上の規則は、簡単なようで、細かい箇所の引っ掛け問題は間違えやすいです。
しかし、覚えれば点が取りやすいので、確実に宅建業法で取っていきましょう!
証明書の種類と携帯、標識の提示、帳簿の備え付け、案内所の提示などがポイントです。
証明書の携帯等 <業者間取引にも適用>
重要事項の説明をする時は、相手方の請求の有無に関わらず、宅建士証を提示しなければならない。
しかし、従業員証明書は取引関係の請求があったときのみ提示すればよい。
従業者証明書
【従業員証明書(様式第8号)】

(引用画像:国土交通省より)
従業者証明書には業務に従事する事務所の名称・所在地・従業者証明書番号等が記載されるが、従業者の住所は記載されない。
なお、宅建士証には、宅建士の住所は記載されるが、勤務先は記載されない。
従業者名簿の備付けと記載事項
また宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業員名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その者の閲覧に供しなければならない。
「従業者名簿」には、下記の事項を記載しなければならない。
1)氏名(「住所」は平成28年改正法で削除)
2)従業者証明書番号
3)生年月日
4)主たる職務内容
5)宅建士であるか否からの別
6)当該事務所の従業者となった年月日
7)当該事務所の従業員でなくなったときは、その年月日
名簿の保存期間は、最終の記載をした日から10年間(作成時ではない!)
帳簿の備付け <業者間取引にも適用>
また宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引があったつど、その年月日、その取引で係る事項などを記載しなければならない。
【主な必要記載事項】
1)取引の年月日
2)取引態様の別
3)取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号・名称(個人の場合はその氏名)
4)報酬の額
5)業者自ら売主となる品確法2条2項に規定する新築住宅の場合
6)取引に関する特約
帳簿の保存期間は、閉鎖後5年間
当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間
標識の掲示 <業者間取引にも適用>
宅地建物取引業者は、事務所以外の場所、案内所などにも標識を提示しなければならない。
標識を提示しなければならない場所
・事務所等(事務所及び専任の宅建士を設置しなければならない案内所等)
・国土交通省令で定める業務を行う場所
・継続的に業務を行うことができる施設で事務所以外のもの
・宅建業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所(分譲地・現場)
・宅建業者が業務に関し展示会や催しを実施する場所
業務に関し展示会を複数の宅建業者が共同で実施する場合でも、すべての宅建業者が自己の標識を提示しなければならない。
宅建業者が案内所を設ける場合
宅建業者は、一団の宅地建物の分譲現場及び案内所の双方に標識を提示しなければならない。
これに対して、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理を案内所を設けて行う場合は、代理者がその案内所に標識を提示しなければならない。
事務所と案内所の標識の違い
専任の宅建士を置くべき場所か否かによって、標識の様式は異なる。
【専任の宅建士を設置すべき案内所の標識】

(引用画像:国土交通省より)
一方、専任の宅建士を置く必要のない案内所に掲げる標識には、「宅建業法37条の2の規定によるクーリング・オフ制度の適用があります」の表示が必要
【専任の宅建士を設置しない案内所の標識】

(引用画像:国土交通省より)
案内所等の届出
案内所は、あらかじめ業務を開始する日の10日前までに、所在地を管轄する都道府県知事と、免許権者の双方に届け出なければならない。
案内所の届出方法
・免許権者が都道府県知事の場合は直接
・国土交通大臣である場合は、届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由
* 注意:一団の宅地の分譲について、売主業者Aが他の業者Bに代理を依頼した場合は、代理業者Bが届け出なければならない。
宅地建物が所在する場所(分譲地)の届出
分譲地などの届け出については、売主である宅建業者が自己の標識を提示する必要があるが、行政庁への届出は不要。
現地案内所のように契約の締結を予定せず、専任の宅建士の設置義務のない案内所については、届出は不要。
しかし、標識の提示は必要。
過去問の解答と解説:「業務上の規制」
本文の解説はいかがでしたか?
序文の問題の解答です。
(1)〜(4)は全て正しいです。
問題35
(1)自ら貸主として賃貸借契約を締結する行為は、宅地建物取引業に該当しない(宅地建物取引業法2条2号)から、宅地建物取引業法上の制約を生じないので、業務に関する帳簿に一定事項を記載する必要はない。
(2)宅地建物取引業者は、「その事務所ごとに」つまり業務に関する帳簿を、主たる事務所の他に従たる事務所にも備えなければならない。
(3)報酬の額は、帳簿の記載事項であり(同法49条、施行規則18条1項7号)、これに違反すると指示処分の対象となる。
(4)従業者名後の「従業者」には、一時的に事務所の補助のために雇用した者お含まれるから、従業者名簿に記載しなければならない(同法48条3項)
(参照:【平成29年 問35】過去問解説より)
自らが貸主とならない宅地建物取引業に該当する場合は、帳簿の記載義務はあります。
一部だけを変えた引っ掛け問題も出題されるので注意してください。
暗記のポイント「業務上の規制」
(1)従業者は、取引関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。
(2)従業者名簿は、事務所ごと(本店、支店ごと)に備え付けて、最終の記載をした日から10年間は保存しなければならず、取引の関係者から請求があったときは、その者の閲覧に供しなければならない。
(3)帳簿は、事務所ごと(本店、支店ごと)に備え付けて、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは、10年間)は保存の義務があり。
(4)標識は、事務所及び業務を行う場所ごとに公衆の見やすい場所に設置する
(5)案内所は、業務開始の10日前までに、その場所を管轄する都道府県知事、及び免許権者の双方へ届け出の必要があり。
宅建士に本気で合格したい人はこちらの記事を読んでください。
宅建の科目別の勉強法!カリスマ講師達が教える合格の学習法とは?
テキストを探している人は、【宅建テキスト2021】独学におすすめは?人気の出版社別4シリーズを徹底比較!
過去問攻略が合格の鍵
【宅建】過去問おすすめ勉強法と問題集!私は過去問攻略で1ヶ月で合格した
通信講座の費用を安くしたい人は
フォーサイトの教育給付金制度で受講料が20%戻った申請方法と注意点
独学で悩んでいる人は、効率よく宅建対策ができる通信講座もおすすめです。
通信講座「宅建合格のコツがわかる無料の体験講座べスト5」で、宅建試験の攻略ポイントがわかります!
宅建合格者がおすすめの合格率の高い宅建【スタディング:STUDYing】、 宅建【フォーサイト】や【ユーキャン】なども見逃せません。