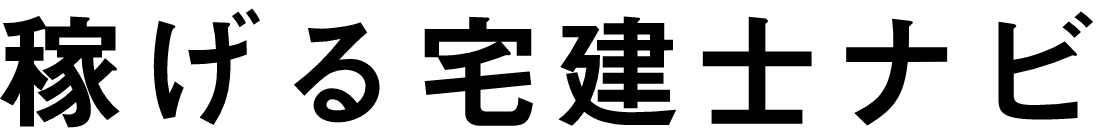宅建試験は50問が出題されます。
科目ごとの足切り点(何点以上取れなければ不合格になる)はなく、総合点で合否が決まる試験です。
ここでは、宅建士の科目別の攻略法と目標点についてお伝えします。

Contents
宅建試験の科目ごとの出題数と目標点
|
科目 |
出題数 |
|---|---|
|
権利関係 |
14問 |
|
法令上の制限 |
8問 |
|
宅建業法 |
20問 |
|
税・その他 |
8問 ※ |
|
合計 |
50問 |
(★「税・その他」では5点免除制度があり)
5点免除とは、不動産の実務経験者向けに、あらかじめ5問分の問題(5点)がプラスされる優遇措置です。
5点免除は、有利な制度なので該当する受験生は、ぜひ活用してください。
★ 5点免除制度について詳しくは >>>> 宅建5点免除講習(登録講習)で宅建の試験を有利にする方法。でも油断禁物!
合格点は平均35点、37点に上がる年もあり
毎年、最低の合格ライン点が公表されていますが、今までは平均35点あれば合格していました。
(参考記事:宅建士の難易度は?合格率とコスパの良さは超穴場の資格と感じる私の経験)
私が受験した2018年度の足切点は、37点でした。
これは点が取りやすい問題が出題されたので、受験生の平均点が上がったからです。
よって宅建の試験対策は、満点を目指すのではなく、目標35点〜37点を取れれば良いです。
科目ごとの足切り点がない宅建は、自分の得意分野で点を稼げるので、苦手科目は捨てることもできる合格しやすい試験です。
合格者が得点を稼ぐ分野は共通している
ここで注目は、実際に宅建に合格した人の点の取り方です。
合格点できる人は、毎年、ほぼ同じ分野で点を取って合格しています。

多くの合格者が共通して強調する試験対策のコツは、
「宅建試験は確実に解ける問題で点を稼ぐ事が合格の近道」です。
宅建試験の4科目と目標点数
試験科目によって目標の点数が違います。
| 試験科目 | 目標点数 |
| 権利関係 14問 | 8〜9点 |
| 法令上の制限 8問 | 5〜6点 |
| 宅建業法 20問 | 18点 |
| 税その他 8問 | 4点 |
| 合計 50問 | 37点 |
(参照:各学校の宅建合格の対策講義より)
一般的に「宅建業法」は、20問のうち9割と目標点数は高いです。
逆に「権利関係」や「税その他」は半分以上と目標点数は低いです。
宅建は4科目ごとに目標点は変わる
宅建は7割以上が過去問から出題されていますが、科目ごとに出題率が変わります。
受験生が比較的、点が取りやすい「宅建業法」や「法令上の制限」からは、過去の問題から多く出題されています。
この2つの科目は、難易度が高く無いので点が取りやすいです。
しかし「権利関係」や「税その他」からは、過去問以外の問題が幅広く出題されているので、点が取りにくい面もあります。
この試験の出題範囲の広さが、宅建士が難しい資格と言われる理由だと思います。
合格に必要な最低限の知識が効率よく学べます。

苦手な科目は、ある程度までは捨てても良いです。
しかし、全部、捨ててしまうと、他の科目で満点近く取らないと総合点に届きません。
苦手な科目でも効率よく、最低限の重要事項は学習する必要があります。
★ 各科目ごとの攻略方法は「宅建の科目別の勉強法!カリスマ講師達が教える合格の学習法とは?」で紹介。
宅建試験は難しくなる傾向、丸暗記は通用しない
宅建の予備校講師も話していた事ですが、ここ数年の宅建試験は難しくなる傾向があります。
宅建試験には、大きく2つの傾向がみられます。
1つ目は過去問題の丸暗記が通じない問題が出題される事です。
・「4つの問いの中で正解肢がいくつあるか?」
正解の個数を聞いてくる試験が、4問択1の形式で出題されます。
この様な問いは、問題文を全て1枝ごとに正確に理解していないと解けません。
特に問題文の意図を正確に読み取る力が必要になり、単に過去問題を丸暗記するだけでは、応用がききません。

2つ目の傾向は、権利関係などで出題される民法の引用例文が長くなる傾向があります。
判決文を読んだ上で答える問題は、答えになる部分を長い引用例から探す必要があります。
読むのに時間がかかると時間切れになります。
解きやすい問題から解く試験テクニックも必要になります。

この様に試験の難易度が上がると、最短の宅建合格は難しいと思われがちです。
しかし、宅建は、「出題のレベルは毎年変わるが、合格している人のレベルは変わらない」試験です。
不動産業の実務経験が無い初心者も多く受験するので、適切な受験対策をすれば点が伸びます。
効率の良い勉強法をすれば、ライバルよりも有利に合格へ近づく事ができます。
宅建士の攻略法は、その人の経歴や学習経験で変わる
宅建士のどの科目を強みにするか?はその人ごとに違います。
例えば、行政書士や司法書士など法律系の勉強をしてきた人であれば、民法の問題は解きやすく、強みになります。
また、不動産業界の経験者であれば、5点免除制度で、「税・その他」の科目は自動的に5点が加算されるので有利です。
また、不動産取引の出題が多い宅建業法も、実際に実務でやっているので理解は早く、初学者よりも勉強時間は少なくて済みます。
私のように建築業界の出身者であれば、建築基準法などの建築分野の出題が多い「法令上の制限」は、勉強しなくても解ける問題が多いです。
過去に会計や経理関係の仕事をしていた人、FPの資格を取得している人であれば、税金の仕組みはわかりやすいです。
宅建士は試験範囲が広いので、自分の経験によって得意分野が分かれます。

過去に資格試験の勉強をしてきた人にとっては、出題範囲が重なるのはチャンスです。
宅建試験は、一概に難しいとは言えないと思います。
ただ、今まで関連する資格を受験した経験も実務経験がない初学者でも、合格のチャンスはあります。
宅建士は7割以上が過去問題から出題されています。
既成概念がなく、新しい知識が頭に入りやすく新鮮な気持ちで勉強できるのは、初学者の強みです。
その人の見方やとらえ方次第で、宅建士の難易度は変わります。
宅建士の出題範囲だけをみて、難しいと諦めてしまわないでください。

★ 宅建士の過去問の対策については >>> 「宅建の過去問攻略法」で必勝の勉強法がわかります!
宅建はマークシートなので難易度は高くない
宅建の試験はマークシート式で、要領良く解答できる人には難易度は高くないです。
4問択1(4問のうち正しい問題を1つ選ぶ)で、合計50問が出題されます。
試験時間は合計2時間です。
解答時間は1問2分が目標。分問題文が、わからなければ飛ばしても問題ありません。
見直しの時間(約20分)を含めると、1問あたり2分で解かないと時間が足りません。
1問あたり4肢あります。
よって問題文は1肢あたり30秒で読まないと間に合いません。
最初は1問あたり2分30秒弱で解く事を目標にして時間を縮めていきましょう。
時間の感覚を身につけるために、時計やストップウオッチで、時間を測りながら勉強する人もいます。

時間を計りながら勉強していると、段々と難しく感じなくなります。
独学でも良いが、時間短縮を考えれば通信講座
時間を買う行為が、通信講座を選ぶ事だと思います。
独学でも宅建試験には合格できますが、効率よく試験勉強をしたい人は、通信講座も検討してみてください。
宅建士を独学で勉強したい人向けに、独学に近い予算のコスパ良しの通信講座があります。
受講生が3万人以上を突破した人気急上昇中の通信講座で、宅建の初心者には特におすすめです。
宅建のスタディング(旧:通勤講座)は、受講料が19,800円で業界で最も安いですが、この講座で合格できた人は多数います。
★「失敗しない宅建士合格法5つのルール」も無料で視聴でき、割引特典もあるので、
スタディング(studying)宅建の体験講座をぜひ試して見てください!
★ 合格率の高さと教育給付金対象の講座で選ぶならば、下記の記事もおすすめです。