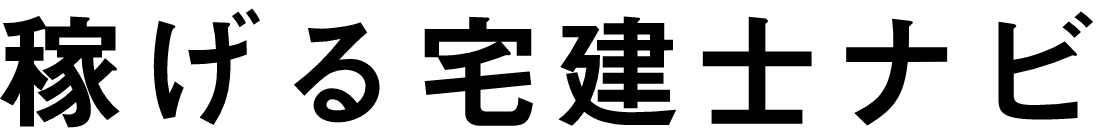今回の宅建士になるための権利関係の過去問解説は「不法行為」についてです。
この「不法行為」は「債務不履行」との違いを理解するのが、学習のポイントです。
不法行為は、過去10年間の宅建士試験で計7問、出題されています。
ここで過去にも出題された問題です。
あなたは、勤務中に会社所有の乗用車を運転し、営業活動のために得意先に向かっている途中で交通事故を起こしてしまいました。
その時に道を1人で歩いていた幼児にも危害を加える結果になりました。
被害者側にも過失がある場合でも、あなたは幼児に対して全額を賠償する必要があるのでしょうか?
幼児の事故なので、親の過失責任も問えるのでしょうか?
続きは本文でみていきましょう!

Contents
不法行為とは
故意または過失により、他人の権利・利益を侵害することにより、損害を生じされる行為を不法行為という。
この原則的な場合のことを、後に説明する特殊的不法行為に対して一般的不法行為という。
(参照:「パーフェクト宅建 基本書」より)
不法行為には、加害者自身の責任となる一般的不法行為、またそれ以外の特殊なケースになる特殊的不法行為の2種類があります。
宅建建物の取引でも債務不履行責任と不法行為責任は、両立して成立すると解釈されています。
不法行為と債務不履行の違いは、対比して理解して下さい。
| 不法行為 | 債務不履行 | |
|
故意または 過失の必要性 |
必要 |
必要 |
|
故意または 過失の立証責任 |
被害者側 |
債権者側 |
| 過失相殺 |
考慮できる (損害賠償が0円になることはない) |
考慮できる (損害賠償が0円もあり得る) |
| 債権者の権利 |
損害賠償請求 |
損害賠償請求・契約解除 |
債務不履行とは、契約をお互いにしていて履行が不能になった場合ですが、不法行為は、相手とは、そもそも契約はしていません。
一般的不法行為とは
一般的な判断能力がある加害者自身の故意、または過失ある行為のことを、一般不法行為といいます。
下記の要件で成り立ちます
1)責任能力がある者が
2)「故意または過失」
3)他人の権利等を侵害し
4)損害を与え
5)行為と損害との因果関係がある
自己責任の原則:人は自分の行為についてのみ責任を負うこと。
故意:結果の予想を認識していても、あえてその行為をすること
過失:不注意によりその結果の発生を認識しないで行為をすること
少なくとも過失が無ければ、不法行為が成立しないという原則を「過失責任の原則」と言います。
故意・過失に対して、損害賠償の請求をする場合は、被害者側が立証する必要があります。
債務不履行は、債権者側でしたよね。
責任能力の存在
不法行為が成立するためには、加害者に責任能力がなければなりません。
責任能力とは、自己の行為が違法なものとして、法律上非難されるものであることを弁識できる能力のことです。
未成年や責任弁済能力のない者は、裁判で責任能力がないと判断された場合は、無罪になることもあります。
未成年者だから責任能力がないとは一概に言えませんが、一般的に責任能力が備わるのは12歳ぐらいからと言われています。
権利侵害(違法性)の存在
法益とは、法的に保護されるべき利益のことです。
権利の侵害といっても、法律によって具体的に○○権と称されていないものでも、何らかの法益が侵害されれば、この要件を満たします。
下記の場合は、違法性がなくなり、不法行為は成立しません。
・正当防衛や緊急避難行為(自分の身を守る為)
・被害者の承諾があるとき(公序良俗の違反にならない常識の範囲)
・正当業務行為(医師の治療行為、スポーツ中の加害行為など)
被害者の承諾があっても、非常識な行為(例えば、ビルから飛び降りると100万あげる)などは認められません。
また、プロボクサーなどが試合中に相手を死なせたとしても、罪に問われないなどは、正当業務行為になるからです。
損害の発生
損害が発生しない限りは、不法行為は成立しません。
精神的損害の賠償のことを慰謝料といいます。
また、その行為があったから損害が発生したという、因果関係(原因と結果の関係)がなければなりません。
損害賠償請求権の発生
不法行為の成立が認められると、被害者から加害者に対する損害賠償請求権が発生します。
損害賠償の2つの方法
・金銭賠償
・原状回復
原則としては、金銭賠償の方法で損害の責任をとります。
損害賠償の範囲
不法行為者が賠償すべき損害の範囲は、加害行為と相当因果関係に立つ損害です。
損害の種類
・積極的損害:財産的損害など被害者が現実に被った損害
・消極的損害:本来ならば得られたであろう利益の喪失
例えば、交通事故に遭って、働けたら得ていたであろう収入を補償するは成り立ちます。
しかし、宝くじを買えなくなったなどは因果関係がないので、成り立ちません。
遅延利息の発生時期
不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時から遅滞に陥ると解されています。
その利率は、年5分の法定利率です。
相殺の禁止
加害者が被害者に対して何らかの債権を持っていても、加害者側から、その債権と相殺することはできません。
しかし、被害者側から相殺することは自由で禁止されていません。
過失相殺
損害賠償額を定める場合、被害者側にも過失があった時は、具体的な公平を図るために、裁判所は、これを斟酌(考慮)することができます。
債務不履行の場合の過失相殺であれば、裁判所は考慮することにしています。
考慮「できる」と「する」は違うので、ニュアンスの違いは覚えておいて下さい。
損害賠償請求権の消滅時効
不法行為への損害賠償請求権は、一定の期間が過ぎれば、時効により消滅します。
・知った時から3年間 (時効期間)
・不法行為の時から20年間 (除斥期間)
除斥期間とは : 権利の行使を一定期間内に制限する制度。中断ということがない点が時効とは異なります。
特殊的不要行為
特殊的不法行為とは、上記の一般的不法行為とは異なる特殊な要件で成立する不法行為のことです。
下記の3種類があります。
・使用者責任(会社が従業員を使っていて従業員の責任を会社が負う場合)
・注文者の責任(工事などを注文した場合)
・土地工作物責任(例えば道を歩いていると、瓦が落ちてくるなどの場合)
使用者責任
使用者責任とは
ある事業のために他人を使用する者(使用者)、または使用者に代わって事業を監督する者は、被用者(従業員)がその事業の執行につき第三者に損害を加えたとき、その賠償責任を負う(715条)
(参照:「パーフェクト宅建 基本書」より)
使用者責任が生ずるのは、被用者が事業を執行した際、第三者へ損害を生じさせた場合のみです。
・成立する要件
1)ある事業のため他人を使用していること
2)被用者が事業の執行につき(業務中)行ったものであること
3)第三者への加害行為でること
4)被用者自身に一般的不法行為の要件が備わっていること
使用者責任を免れる場合
しかし、使用者側が下記を証明した場合は、使用者責任を免れます。
・使用者が被用者の選任及び監督について相当の注意をしたこと
・または相当の注意をしても損害が発生した場合
法律では定められていますが、一般的には、使用者責任を免れることは難しいです。
使用者は被用者へ求償できる
もし、使用者または代理監督者が、被害者に損害賠償をした時は、被用者(従業員)に対して、妥当と認められる程度まで求償することができます。
全額を弁償するのは難しいですが、被用者も責任を負う必要があります。
求償とは:賠償または償還を求めることです。代わりに賠償金を支払った人が、被害者への支払い後で、損害を起こした人に請求することです。
注文者の責任
請負人の行為については、注文者は原則として責任を負いません。
しかし、注文者が請負人に指示、または注文に過失があったために、他人に損害を与えた場合は、責任を負います。
土地工作物責任
土地工作物責任とは、
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があるために、他人に損害を生じさせたときは、その工作物の占有者または所有者が加害者に対して、その賠償責任を負う。(717条)
(参照:「パーフェクト宅建 基本書」より)
工作物責任が成立する要件
1)土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったこと
2)他人に損害が生じたこと
3)1)と2)の間に因果関係があること
一次的には、占有者が損害賠償責任を負います。
しかし、占有者は、自ら損害の発生を防止するために必要な措置を講じていたことを証明すれば、責任を免れます。
もし、上記のように占有者が免責事由を証明したときは、二次的に所有者が責任を負います。
所有者は、自分に過失が無いことを証明しても、責任を負う必要があります。
これを無過失責任といいます。
一次的な責任者は免責が適応されれば、責任を負う必要がないですが、二次的な責任者は、最後の砦なので、絶対に責任を負う必要があります。
宅建士過去問まとめ:不法行為
以上、不法行為の解説はいかがでしたか?
下記が序文の答えの解答です。
過失相殺は、広く被害者側(被害者の父母等)に過失がある場合に考慮される。
(参照:【平成24年 問9-4項】過去問解説より)
被害者本人だけでなく、身分上または生活関係上被害者と一体の者を加えた被害者側に過失があれば、過失相殺できます。
この場合は幼児の父母にも目を離した過失があるので、過失相殺できます。
また使用者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任もあります。
勤務中の事故なので、使用者側が責任をとります。
使用者が損害を賠償した場合、使用者は被用者(雇用者)に対して信義則上相当と認められる限度で求償できます。
使用者は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し求償の請求をすることができる
(参照:【平成24年 問9-3項】過去問解説より)
交通事故は、過失相殺されたとしても負担は残ります。
あなたの交通事故の損害を代わりに負担した会社から、あなたは支払える範囲で賠償を求められる可能性はあります。
返済は給料天引きで支払うことになるかもしれません。
宅建に一発合格した経験から書いた「宅建独学おすすめの勉強法」を紹介!
最短で宅建に合格したノウハウ
【宅建】過去問おすすめ勉強法と問題集!私は過去問攻略で1ヶ月で合格した
宅建試験は、テキスト選びで勝負が決まる?
【宅建テキスト2021】独学におすすめは?人気の出版社別4シリーズを徹底比較!
独学で学力が伸び悩む人は、効率よく宅建対策ができる通信講座もおすすめです。
通信講座「宅建合格のコツがわかる無料の体験講座べスト5」で、宅建試験の攻略ポイントがわかります!
宅建合格者がおすすめの合格率が高い講座とは?
宅建【スタディング:STUDYing】、 宅建【フォーサイト】の無料体験講座はおすすめです。
通信講座の費用が気になる人は「宅建士の通信講座を安くする方法とは?教育給付金制度で授業費用の20%が戻る!」の方法もあります。